【禅宗の歴史】
禅宗は、菩提達磨(ぼだいだるま)を始祖として、「教外別伝(きょうげべちでん)・不立文字(ふりゅうもんじ)」を掲げ、釈尊の説いた経論にはよらず、座禅によって悟りを得ようとする宗派です。
禅宗は『大梵天王問仏決疑経(だいぼんてんのうもんぶつけつぎきょう)』という経典をを拠りどころとしています。それによると、
「釈尊(お釈迦様)が涅槃の時、聴衆の一人が一枝の睡蓮(すいれん)を釈尊に捧げた。釈尊は黙ってそれを受け取り、拈(ひね)って大衆に示した。その場の大衆は釈尊の意図するところが分からなかったが、摩訶迦葉(まかかしょう)一人がそれを理解して破顔微笑(はがんみしょう)した(拈華微笑=ねんげみしょう)。そこで釈尊は、『正法眼蔵、涅槃妙心、実相無相、微妙の法門有り。不立文字、教外別伝にして、摩訶迦葉に附属(ふぞく)す』といって、仏の悟った深遠微妙(じんのんみみょう)の法門は経論・言辞によらず、ただちに以心伝心をもって法を摩訶迦葉に附属した」
ということです。これが「教外別伝・不立文字」のはじめで、禅宗はここから始まったとしています。
南インドの僧であった達磨は、この教えを中国に伝えようと、西暦520年頃に中国(当時の北魏)に入りました。そして嵩山(すうざん)少林寺(有名な小林拳の寺)の石窟で壁に向かって9年間の座禅を修し、中国禅宗の開祖となりました。
日本へ禅宗が初めて伝わったのは、奈良時代の道昭によるものです。道昭は西暦653年に中国(当時の唐)に渡り、法相宗・成実宗とともに禅も学び、日本に帰ってからこの二宗とともに禅を伝えました。
このように禅宗は当初、他宗に付随する形で伝えられましたが、鎌倉時代にいたって、栄西(えいさい)が臨済宗を、道元が曹洞宗を開きました。この他に、中国僧の隠元(いんげん)が伝えた黄檗宗(おうばくしゅう)という宗派もあります。
![]()
 【高祖】希玄道元
【高祖】希玄道元
【太祖】瑩山紹瑾(けいざんじょうきん)
【本尊】釈迦牟尼仏が多く、特にこだわりがない
【経典】『法華経』『涅槃経』『華厳経』『般若経』など
【本山】永平寺、総持寺
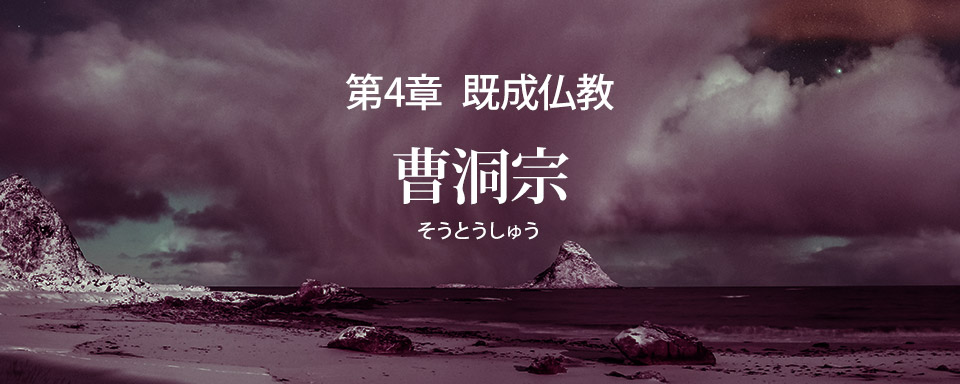
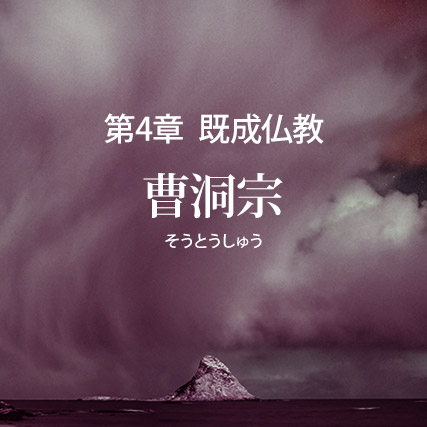

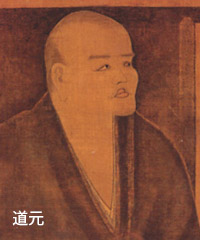 日本曹洞宗は、鎌倉時代に、5年間宋に留学した道元によって伝えられました。
日本曹洞宗は、鎌倉時代に、5年間宋に留学した道元によって伝えられました。