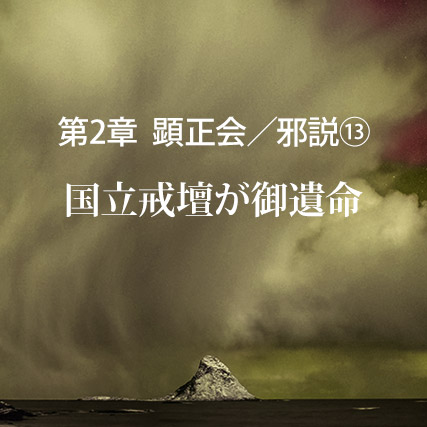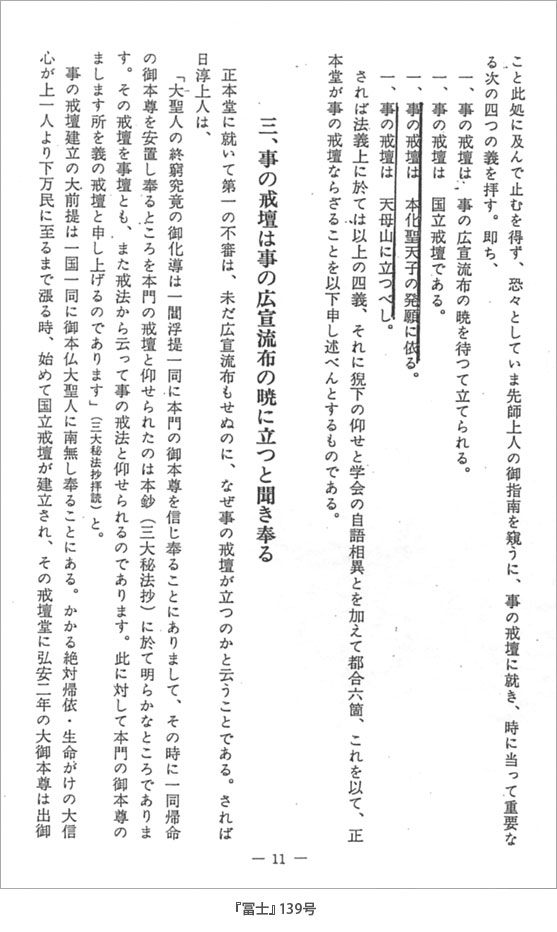(1)「もし日蓮大聖人の三大秘法が、一国の安泰、そして世界の平和、全人類の成仏のための唯一の正法であることが理解されたら、国家がこの仏法を守護するのは、当然の義務となりましょう。(中略)この大御本尊を、仏法有縁の国として日本国が、世界のため全人類のために、国運を賭しても守り奉る。これが国立戒壇建立の大精神であります」(第24回総会 冨士268号)
![]()
(2)「そもそも三大秘法抄・一期弘法付属書は、戒壇建立の条件として三大秘法が国家的に受持された時、すなわち三大秘法が国教となった時を、明確に示しておられる。(中略)すなわち『国教でない仏法に国立戒壇はあり得ない』のではなく、『国教にすべき仏法であるから国立戒壇を建立せねばならぬ』のである」(冨士250号)
![]()
(3)「御付嘱状の『国主此の法を立てらるれば』、また四十九院申状の『国主此の法を用いて』とは、まさに『国教にすべし』との御意ではないか。また三秘抄の、王法が冥ずる『仏法』、王臣一同が受持する『本門三大秘密の法』、勅宣・御教書を以って擁護(おうご)すべき『戒壇の大御本尊』とは、まさしく国教そのものではないか。そして、国家が根本の指導原理として三大秘法を受持擁護するその具体的発現が、国立戒壇の建立である。ゆえに、国教だからこそ国立戒壇が必要なのである」(なぜ学会員は功徳を失ったか)
![]()
(4)「現憲法に気兼ねして、『国教』を禁句のごとく扱う必要はない。第五十六代日淳上人は堂々と『真に国家の現状を憂うる者は、其の根本たる仏法の正邪を認識決裁して、正法による国教樹立こそ必要とすべきであります』と御指南されているではないか」(冨士312号)
![]()
(5)「憲法改正は、国会議員の3分の2以上が賛成し、国民投票で過半数を得ればできるじゃないか。だから、国民の過半数が戒壇の大御本尊を信じ、国立戒壇を熱願すれば、御遺命はいよいよ実現するのです。国民の意志を無視して国会議員の身が持つかね」(顕正新聞 H5.1.5号)
![]()
(6)「すなわち広宣流布の時には、日蓮大聖人の仏法を基本原理とする憲法が制定されなくてはならぬ。この時が、本門戒壇建立の時なのである」(冨士312号)
![]()
(7)「広宣流布達成の暁の憲法は、前文においても今のようなまやかしではない。(中略)すなわち『日本国は、国家の安泰と国民の幸福のために、日蓮大聖人の仏法を国教と定める』、まずこのことが謳われなければいけない。さらに、『日本国は、日蓮大聖人が全人類に授与された本門戒壇の大御本尊を、全人類のために守護することを国家目的とする』と」(顕正新聞 H13.2.5号)
![]()
(8)「『勅宣』とは国主である天皇陛下の正式のおことば、御教書とは時の政権運用の立場に在るものの意思表明であります」(冨士250号)
![]()
(9)「もし国民が国主であるとすれば、日本には一億二千万人の国主がいることになる。国主は一人でなければ成り立たない。ゆえに報恩抄には『国主は但一人なり、二人となれば国土おだやかならず』とある」(最後に申すべき事)